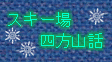 |
リフト★ 一本勝負! |
このスキー場に 行け! |
ゲレンデ ヌーヴォー |
極私的 スキー場批評 |
スキー場 歴訪記録 |
|
| 雪の素材集 |
雪山 千夜一夜物語 |
websiteの 道具箱 |
リンク集 | スキー場 インディーズ |
パンフ原色図鑑 【別サイト】 |
| http://yomo-ski.sports.coocan.jp/ | サイトマップ |
|
|
| 本ページは、本省令の制定時の条文を記載しています。 当該省令が掲載されている「官報 昭和62年3月2日 号外第16号」から文字起こしをしています。 官報は紙ベースですが、本ページでは「官報情報検索サービス」において提供されている官報のスキャン画像を元にしています。 なお、官報は、表組みも含め、縦書きです。(数式の部分は横書き) 極力、官報のとおりに再現するよう努めていますが、当方のミスタイプなどにより、本来の文言とは異なる可能性がありますので、ご了承ください。 また、現在は条文が異なっています。最新版をご確認いただけるよう、お願いします。 |
| 各章へジャンプ> |
| 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第ニ章 |
| 第二章 構造 第一節 普通索道 第一款 索道線路等 (索道の方式) 第七条 普通索道の方式は、交走式、複線自動循環式又は単線自動循環式としなければならない。 (架設場所) 第八条 普通索道は、人家、危険物貯蔵所又は多数の人が集合する場所から水平距離四メートル以内の区域の上空に架設してはならない。ただし、やむを得ない理由のある場合であつて物の落下による危険を防止するための保護設備を設けたときは、この限りでない。 (搬器と建造物との間隔) 第九条 普通索道の搬器(懸垂部を除く。)とこれに近接する建造物(乗降場を除く。)との間隔は四百五十ミリメートル以上となるようにしなければならない。 (支索等の高さ) 第十条 普通索道の支索又は支えい索は、停留所以外の場所において、これに懸垂する搬器の下端が地表面から五メートル以上の高さになるように設けなければならない。 2 普通索道のえい索及び平衡索は、停留所以外の場所において、地表面から五メートル以上の高さになるように設けなければならない。 3 前二項の規定にかかわらず、さく等の立入り防止の措置を講じた箇所又は土地の状況により人の立ち入るおそれがない箇所においては、前二項に規定する高さを四百五十ミリメートルまでとすることができる。 (支索等のこう配) 第十一条 普通索道の支索(交走式の普通索道(以下「交走式普通索道」という。)に係るものを除く。)又は支えい索のこう配は、水平線と三十度以内でなければならない。ただし、運輸大臣が告示で定める握索装置を有する普通索道の支索または支えい索にあつては、その勾配を水平線と四十度以内とすることができる。 2 複線自動循環式の普通索道(以下「複線自動循環式普通索道」という。)の支索には、少なくとも一停留所において、搬器がえい索を握索した直後の短区間に、搬器が当該線路を走行したときに起こる支索の最大傾斜角以上の上りこう配(以下「試験こう配」という。)を設けなければならない。 3 単線自動循環式の普通索道(以下「単線自動循環式普通索道」という。)の支えい索には、少なくとも一停留所において、支えい索を握索した直後の短区間に水平こう配又は上りこう配を設けなければならない。 (えい索の架設) 第十二条 複線自動循環式普通索道のえい索は、一搬器の圧索機が各えい索のそれぞれの接合部を同時に握索しないように架設しなければならない。 (運転速度) 第十三条 普通索道の構造は、その運転速度が、交走式普通索道にあつては五メートル毎秒、複線自動循環式普通索道にあつては二メートル毎秒、単線自動循環式普通索道にあつては五メートル毎秒を超えないものでなければならない。 (搬器の出発間隔) 第十四条 複線自動循環式普通索道及び単線自動循環式普通索道の構造は、搬器の出発間隔が、複線自動循環式普通索道にあつては一分、単線自動循環式普通索道にあつては十二秒又は一・五秒に定員を乗じた時間のいずれか長い時間以上となるものでなければならない。 (索条の設備) 第十五条 交走式普通索道及び複線自動循環式普通索道の索条の設備は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 一条の支索のほかに搬器を支持することができる強さを有する索条があること。 二 一えい索が切れても他のえい索により搬器を安全に移動させることができること。 三 支索の一端には、二重引留装置を設けること。 四 支索及び平衡索又はえい索の一端には、緊張設備を設けること。 五 おもりを使用する支索の緊張設備は、次のいずれかによること。 イ 支索とおもりとの間に可とう性の緊張用索条を設け、かつ、支索と緊張用索条との接合箇所は二重装置とすること。 ロ 支索とおもりとの間にてこ式調整装置を設け、かつ、支索と当該装置との接合箇所は二重装置とすること。 2 単線自動循環式普通索道の索条の設備は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 支えい索の素線の切断、腐食等を検出するための装置であつて運輸大臣が告示で定めるものを設けること。 二 支えい索の一端には、緊張設備を設けること。 三 おもりを使用する支えい索の緊張設備は、支えい索とおもりとの間に可とう性の緊張用索条を設け、かつ、支えい索の緊張用索条とおもりとの接合箇所は二重装置とすること。ただし、緊張用索条を二条以上とする場合は、この限りでない。 3 前二項の規定にかかわらず、線路の傾斜こう長が百メートル以下の場合には、交走式普通索道にあつては支索の両端に二重引留装置を設けることにより第一項第四号の緊張装置を、単線自動循環式普通索道にあつては前項第二項の緊張装置を設けないことができる。 (索条の強度等) 第十六条 普通索道の索条は、鋼線をより合わせたものであつて、搬器の運転に十分に耐え、索条を支持する滑車に適合したものでなければならない。 2 普通索道の支索は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 ロックドコイル形又はヘルクレス形のものであつて麻心又は合成繊維心がないものであること。 二 主たる素線の平均引張強さが毎平方ミリメートルにつき二百キログラム以下のものであること。 三 線路の途中で継ぎ合わせてないものであること。 3 普通索道の支えい索は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 ウォーリントンシール形のものであつて合成繊維心を有するものであること。 二 主たる素線の平均引張強さが毎平方ミリメートルにつき百九十五キログラム以下のものであること。 三 長手継ぎにより継ぎ合わせたものであつて二以上の箇所で継ぎ合わせてないものであること。 4 普通索道のえい索、平衡索及び緊張用索条は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 可とう性のものであつて麻心又は合成繊維心を有するものであること。 二 主たる素線の平均引張強さが毎平方ミリメートルにつき百九十五キログラム以下のものであること。 三 合成繊維心を有するものにあつては、熱処理をしないものであること。 5 普通索道の索条(支索及び緊張用索条を除く)及びこれを構成する上層素線の直径は、次の式に適合するものでなければならない。(★下の図は書き換え予定) 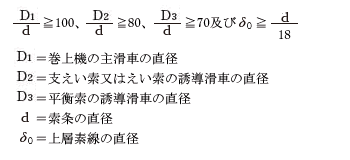 第十七条 普通索道の索条は、次の安全係数に関する計算式に適合するものでなければならない。 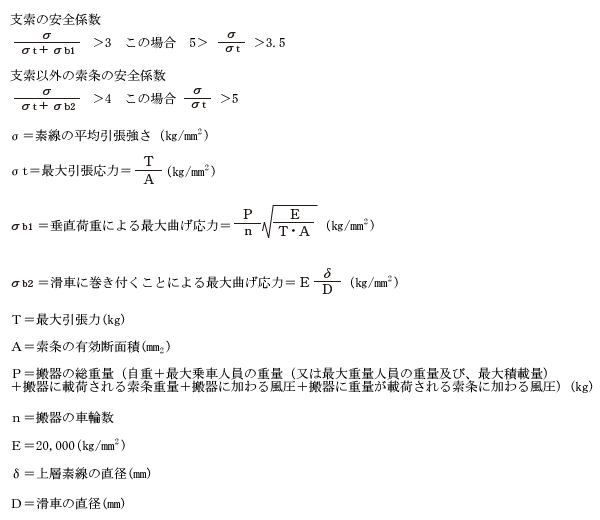 2 前項の計算をする場合の最大引張応力及び最大曲げ応力は、次に掲げる荷重を考慮して計算するものとする。 一 索条の自重及び緊張用おもりの重量 二 搬器の自重並びにその最大乗車人員の重量(人は、一人平均六十キログラムとして計算する。以下同じ。)又は最大乗車人員の重量及び最大積載量 三 搬器及び索条の投影面積の一平方メートルにつき、搬器については五十キログラム、索条については三十キログラムとして計算した風圧 四 支索用シュー、滑車等における摩擦力の総和 五 支えい索又はえい索の起動時における増加引張力 (支柱の強度等) 第十八条 普通索道の支柱の強度は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 次の荷重が同時に加わるものとして計算した加重に耐えること。 イ 支柱の自重による垂直荷重 ロ 索条の重量、搬器の自重並びにその最大乗車人員の重量又は最大乗車人員の重量及び最大積載量による垂直荷重 ハ 支柱の部材、搬器及び索条の投影面積の一平方メートルにつき、平面については五十キログラム、円筒面については三十キログラムとして計算した風圧による水平荷重 ニ 索条に傾斜があるため、索条の引張力によつて生ずる垂直荷重及び水平荷重 ホ 支柱頂部において索条の運転によりその方向に加わる水平荷重 二 次の荷重が同時に加わるものとして計算した加重に耐えること。 イ 前号イの垂直荷重 ロ 索条の重量による垂直荷重 ハ 支柱の部材、搬器及び索条の投影面積の一平方メートルにつき、平面については二百キログラム、円筒面については百二十キログラムとして計算した風圧による水平荷重 ニ 前号ニの垂直荷重及び水平荷重 2 普通索道の支柱は、鉄構造、鉄筋コンクリート構造又はこれと同等以上の耐久力を有するものでなければならない。 3 普通索道の支柱は、支柱間の線路の傾斜こう長が千五百メートルを超えないように設けなければならない。 4 普通索道(単線自動循環式普通索道を除く。次項及び第六項において同じ。)の支柱の支索用のシューの曲率半径は、支索の直径の三百倍(運転速度が三・六メートル毎秒以下の普通索道にあつては二百倍)以上のものであり、かつ、運転により生ずる搬器の求心加速度が一・五メートル毎秒以下となるものでなければならない。 5 普通索道の支索が支柱の支索用シューに及ぼす単位面積あたりの圧力は、毎平方センチメートルにつき二十キログラム以下でなければならない。 6 普通索道の支柱上の支索の屈折角は、搬器を運転する際に十五度を超えないようにしなければならない。ただし、連続型支柱を設け、その支索用シューの曲率半径を支索の直径の五百倍以上とする場合は、この限りでない。 7 普通索道の支柱の受索輪は、支柱上の支えい索又はえい索の屈曲角が三度(運転速度が三・六メートル毎秒以下の普通索道にあつては、五度)を超えないように設け、その直径を二百五十ミリメートル以上としなければならない。 8 運転速度が三・六メートル毎秒を超える普通索道の支柱の受索輪の溝には、支えい索又はえい索に適合した軟質ライナーを使用しなければならない。 9 普通索道の支柱には、索道事業者の名称又は記号、支柱番号及び建設年月を表示しなければならない。 (保護設備) 第十九条 電線路、鉄道、道路(交通量の少ないものを除く。)又は河川湖沼(停留場(交通量の少ないものを除く。)の外側から水平距離四メートル以内の区域の上空に普通索道を架設しようとするときは、物の落下による危険を防止するための保護設備又は適当な保安設備を設けなければいけない。 (災害防止設備) 第二十条 普通索道には、必要に応じ、雪崩等の自然災害から索道施設を保護するための災害防止設傭を設けなければならない。 |
| 第二款 停留場 (停留場) 第二十一条 普通索道事業(普通索道による索道事業をいう。以下同じ。)の停留場には、旅客の乗降に支障を及ぼすおそれのないよう乗降場その他の相当な設備を設けなければならない。 第二十二条 複線自動循環式普通索道及び単線自動循環式普通索道の停留所は、線路全体を監視することができる位置に設けなければならない。ただし、線路全体を監視することができる一に停留所を設けることができない場合は、線路全体を監視することができる適当な位置に監視所が設けられていればよい。 |
|
第三款 原動設備 (主原動機) 第二十三条 索道には、主原動機のほか、予備原動機を設けなければならない。 2 普通索道の主電動機の出力は、次の計算式に適合するものでなければならない。 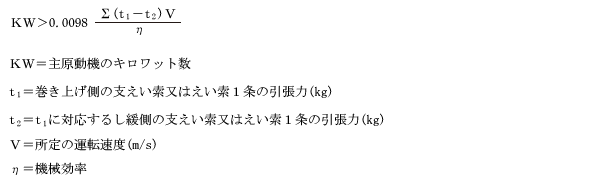 3 前項の巻き上げ側の支えい索又はえい索一条の引張力及びこれに対応するし緩側の支えい索又はえい索一条の引張力は、次に掲げる荷重を考慮してとの差が最大となる場合(以下「最大荷重条件」という。)におけるものでなければならない。 一 支えい索又はえい索及び平衡索の自重並びに支えい索または平衡索の緊張用おもりの自重 二 搬器の自重並びにその最大乗車人員の重量又は最大乗車人員の重量及び最大積載量 三 搬器並びに支えい索又はえい索及び平衡索の投影面積の一平方メートルにつき、搬器については五十キログラム、支えい索又はえい索及び平衡索については三十キログラムとして計算した風圧 四 支えい索又はえい索及び平衡索に係る滑車等における摩擦力の総和 五 支えい索又はえい索の起動時における増加引張力 4 電気を動力とする普通索道の主電動機は、電源電圧が十%降下した場合においても、最大荷重条件において所定の運転速度で運転することができるものでなければならない。 5 第一項の予備原動機は、最大荷重条件において正常に起動できるものでなければならない。 (速度制御装置) 第二十四条 運転速度が三・六メートル毎秒を超える交走式普通索道及び自動運転を行う交走式普通索道には、次の基準に適合する速度制御装置を設けなければならない。 一 加速度及び減速度が〇・三メートル毎秒毎秒を超えないものであること。 二 リアクトル制御方式若しくはワードレオナード制御方式のもの又はこれらと同等以上の制御能力を有するものであること。 三 自動運転を行う交走式普通索道であつて停電その他の理由により自動運転が停止した場合に主原動機で自動運転を再開するものに使用するものにあつては、自動的に自動運転の行程に復帰することができるものであること。 (巻上機) 第二十五条 運転速度が三・六メートル毎秒を超える普通索道の巻上機の主滑車の溝には、支えい索又はえい索に適合した軟質ライナーを使用しなければならない。 2 運転速度が三・六メートル毎秒を超える交走式普通索道には、えい索の引張力を同一にさせるための装置を巻上機に設けなければならない。 |
|
第四款 搬器 (搬器) 第二十六条 普通索道の搬器は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 鉄構造又はこれと同等以上の強度を有するものであつて予想される最大荷重に対し十分に耐えるものであること。 二 搬器が停留所以外の箇所で停止した場合に人を安全に救助することができるものであること。 三 普通索道事業に使用する搬器にあつては、次に掲げるところによること。 イ 燃焼するおそれの少ないものであること。 ロ 前部及び後部に標識灯が設けられていること。ただし、昼間において天候の状態により搬器の識別が困難な場合及び夜間に運転を行わない普通索道にあつては、この限りでない。 ハ 窓は、旅客が容易に脱出することができない構造であること。 ニ 客室内には、照明設備が設けられていること。ただし、夜間に運転を行わない普通索道にあつては、この限りでない。 へ 普通索道事業者の名称又は記号、搬器番号、自重、最大乗車人員又は最大乗車人員及び最大積載量並びに製造年月が記載されているものであること。 四 外部から見やすい箇所に非常用標識灯が設けられていること。ただし、交走式普通索道並び昼間において天候の状態により搬器の識別が困難な場合及び夜間に運転を行わない普通索道であつて手旗等が設けられているものにあつては、この限りでない。 2 交走式普通索道及び複線自動循環式普通索道の搬器は、前項各号に掲げるもののほか、次の基準に適合するものでなければならない。 一 車輪が支索からはずれても搬器が墜落するおそれがないものであること。 二 走行部と懸垂部の連結部が破損しても搬器が墜落するおそれのないものであること。 三 車輪は、支索が傾斜してしても常に荷重を均等に分布させることができる構造を有し、かつ、その直径が二百ミリメートル以上のものであること。たさし、ロックドコイル形の支索を使用する場合の車輪の直径は、百五十ミリメートルまで減ずることができる。 四 車輪の溝の深さは、支索の直径以上であること。ただし、運転速度が三・六メートル毎秒以下の普通索道(単線自動循環式を除く。次号について同じ。)にあつては、この限りでない。 五 急停止した場合に動揺を少なくするための減速装置を有するものであること。ただし、運転速度が三・六メートル毎秒以下の普通索道にあつては、この限りでない。 六 扉は、索道係員に限り開閉することができるものであること。 七 普通索道事業(単線自動循環式普通索道に係るものを除く。)に使用する搬器にあつては、次に掲げるところによること。 イ 手動式の扉には、ニ個の閉鎖器が設けられていること。 ロ 客室内の面積は、旅客一人につき平均〇・一八平方メートル以上であること。ただし、客室内の高さが二メートル以上ある場合は、平均〇・一六平方メートルまで減ずることができる。 ハ 客室内に立席を設ける場合には、つり革その他身体を支えるための適当な設備が設けられていること。 八 ニ個以上の搬器には、支索を点検することができる設備が設けられていること。 3 単線自動循環式普通索道の搬器は、第一項各号に掲げるもののほか、次の基準に適合するものでなければならない。 一 立席が設けられていないこと。 二 扉は、自動開閉式であること。 |
| 第五款 握索装置等 (握索装置) 第二十七条 複線自動循環式普通索道の握索装置は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 搬器の動揺、積載が空の多少、索条の傾斜、索条および握索装置の凍結、索条の塗油等の状態が最悪のときでもえい索を完全に握索し、その耐滑動力がえい索条の滑動力の三倍以上であり、かつ、えい索に損傷を与えないものであること。 二 ニ条以上のえい索に対しニ種以上の異なる方式の握索機を用い、それぞれのえい索に対して少なくとも一個の握索機は、搬器の動揺等により耐滑動力が変わらないものであること。 三 一えい索が切れても他のえい索により搬器を移動することができるものであること。 2 単線自動循環式普通索道の握索装置は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 搬器の動揺、積載が空の多少、索条の傾斜、索条および握索装置の凍結、索条の塗油等の状態が最悪のときでも支えい索を完全に握索し、その耐滑動力が支えい索条の滑動力の三倍以上であり、かつ、支えい索に損傷を与えないものであること。 二 ニ個以上の握索機を用い、当該握索機は、搬器の動揺等により耐滑動力が変わらないものであること。 三 一個の握索機により搬器を移動することができるものであること。 3 交走式普通索道の接続装置は、少なくともえい索の一条と搬器をソケット式又はこれと同等以上の強固な方法により連結するものでなければならない。 |
|
第六款 保安設備 (保安設備) 第二十八条 普通索道には、次に掲げる保安設備を設けなければならない。 一 速度計 二 風速計 三 保安通信設備 イ 停留所、搬器、監視所及び巻上機運転室相互間(搬器相互間を除く。)の通信設備(拡声器等によりこれらの間の連絡を確保することができる場合を除く。) ロ 索道の設備の整備等に従事する索道係員が危険予防のための連絡をすることができる通信設備(拡声器等によりこれらの間の連絡を確保することができる場合を除く。) 四 原動設備の常用制動装置、原動軸に作用する非常用制動装置及び原動滑車に作用する非常用制御装置 五 電気を動力とする普通索道にあつては、原動軸に作用する非常用制動装置又は原動滑車に作用する非常用制動装置のいずれかが動作した場合に巻上機用電動機の電源を遮断する装置 六 支索、支柱及び停留所の避雷装置 七 搬器が停留所以外の箇所で停止した場合に人を安全に救助することができる装置 2 前項第三項イの通信設備は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 専用の回線を設けること。 二 常用電源のほか相当の予備電源を設けること。 三 巻上機運転室においては、運転者が運転に支障を来さないで操作することができること。 3 第一項第四号の原動軸に作用する非常用制動装置又は原動滑車に作用する非常用制動装置は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 次のいずれかに該当する場合に自動的に動作すること。 イ 支索若しくは支えい索が急激に伸びた場合又は支索が切れた場合 ロ 支索若しくは支えい索に異常に強い引張力を生じた場合 ハ 所定の運転速度を、運転速度が三・六メートル毎秒を超える普通索道にあつては十五パーセント、その他の普通索道にあつては二十パーセント以上超えた場合 ニ 交走式普通索道にあつては、搬器が所定の停止位置を越えて走行する場合 ホ 電気を動力とする普通索道にあつては、停電、過負荷その他故障のため巻上機用電動機の機能が停止した場合 二 巻上機運転室、停留所その他保安上必要な箇所において索道係員が迅速に操作することができること。 第二十九条 交走式普通索道には、前条第一項各号に掲げるもののほか、次に掲げる保安設備を設けなければならない。 一 搬器位置表示器 ニ 搬器接近警報装置 三 停留所及び巻上機運転室相互間の搬器出発合図装置 四 停留所侵入速度減速装置 イ 運転速度が三・六メートル毎秒を超える交走式普通索道にあつては、速度制御装置と連動して減速するための装置 ロ 運転速度が二・五メートル毎秒を超え三・六メートル毎秒以下の普通索道にあつて自動運転を行うものにあつては、速度制御装置と連動して減速するための装置 ハ イ及びロに掲げる交走式普通索道以外の交走式普通索道であつて二・五メートル毎秒を超えるものにあつては、停留所入口より三十メートル以上離れた箇所において、二・五メートル毎秒以下の速度に減速するための装置 第三十条 複線自動循環式普通索道及び自動循環式普通索道には、第二十八条に掲げるもののほか、次に掲げる保安設備を停留所に設けなければならない。 一 搬器を送り出す際、握索装置が支えい索又はえい索を完全に握索するための装置 二 握索装置が握索装置が支えい索又はえい索を完全に握索しなかつた場合に自動で気に運転を停止するための装置 三 搬器が到着した際、握索装置が支えい索又はえい索を完全に放索しない場合に安全を停止するための装置であつて、搬器が安全に停止するための余裕距離が設けられているもの 四 交互発車連動装置 五 握索装置が支えい索又はえい索を握索するため、搬器を支えい索又はえい索と同一速度で走行させるための装置 六 搬器が到着して放索した際、後続搬器と衝突しないための逆走防止装置 七 すべての搬器を留置することができる適当な設備 八 握索技が支えい索の接合部を握索しないための装置(単線自動循環式普通索道の停留所に限る。) 九 扉が完全に閉じていない場合に搬器を出発させないための装置(単線自動循環式普通索道の停留所に限る。) 2 複線自動循環式普通索道には、第二十八条第一項各項及び第一項各号に掲げるもののほか、次に掲げる保安装置を設けなければならない。 一 脱索防止装置 二 握索装置に異常を認めた場合に第十一条第三項の規定により設けた短区間において直ちに運転を停止させるための装置 |
|
第七款 雑則 〈工作物の強度) 第三十一条 普通索道の索条及び支柱以外の工作物は、それぞれについて予想される最大荷重に対し、十分耐える強度を有するものでなけれぱならない。 (準用規定) 第三十二条 普通鉄道構造規則(昭和六十二年運輸省令第十四号)第三章第二節、第三節、第五節(第百八条、第百九条第一項、第百十条第二項及び第百十四条に隈る。)及び第六節(第百十七条第一項を除く。)の規定は、普通索道について準用する。この場合において、同規則第百八条、第百九条第一項、第百十条第二項及び第百十四条中「変電所」とあるのは「変電所及び配電所」と読み替えるものとする。 |
|
|
| 各章へジャンプ> |
|
|